2012年2月―NO.108
柔らかいスフレで、スプーンですくうと、かすかに泡のような囁きが聞こえた。
そっと舌に載せると淡雪のように消え、消えた直後にチーズのコクが立ちのぼる。
その旨みは、去って行く懐かしい人の後ろ姿のように、いつまでも後を引いた。
アルパジョンの「朝の八甲田」
デパートの洋菓子売り場を通り過ぎようと思ったら、特設のブースのまわりがやけに賑わっていた。覗くと試食をやっていて、集まった人がプラスチックの小さなスプーンで掬ったものを口に運んでは、微笑んだり、頷いたりしている。
 アルパジョンの「朝の八甲田」 |
「私もください」
次から次へと、かなりの勢いで売れて行く。
「あ、これテレビで見た」
「前に森公美子が紹介してたよね」
と、声がする。
看板を見た……。
「朝の八甲田」と書いてある。
「青森しなやかチーズけーき」
「テレビ、雑誌で話題」
「ネット通販総合ランキング独占」
なんだか華々しい。
私は食べ物の味に関して、マスコミの評判を信じない。けれど、その試食のスプーンの上のものを見ると、目が離せなくなった……。
すくったアイスクリームのようにもろもろとし、色はマスクメロンの果肉のような明るいオレンジ色に輝いている。
看板のアップの写真で見ると、爽やかなレモン色のカップに入ったチーズケーキが、表面張力でこんもりと盛り上がり、今にもカップの縁から溢れそうである。光を浴びたケーキの表面はなめらかで、弾力がありそうだ。揺らしたらムースのように柔らかく揺れるのだろうか……。
柔らかさや弾力を妄想しながら、私はその場に立ち止まっていた。そんな私の気持ちを見てとったのだろう。お店の人が私の鼻先に試食のスプーンを差し出した。スプーンの上で、アイスクリームのようなものが、かすかに揺れた。
私は黙って受け取り、口に入れた。
「……」
それは舌の上で、なめらかなクリームに変わり、噛むことも飲み込むこともせぬまま、淡雪が消えるごとく舌に浸みこんで消える。その消える間際に、まるで思い出したかのように、突然、濃厚なミルクのコクが出て、
(あっ、チーズだ!)
と、感じる。すると、口の中にじゅわーんと唾液がわいて、なんだか去って行く人の後ろ姿を追いかけるみたいに、いつまでもコクと旨みの印象が後を引く。
そして、ふと、思い出した……。
私が四、五歳の頃、わが家の二階に大学生が下宿していた。北海道からやってきた兄弟の学生さんが二人いた。 二人とも体格がよく、階段をのしのしと降りて来ては、
「おばさん、ちょっと出かけまーす」
と、母に声を掛けて行った。
その二人がよく、友だちを引き連れて帰って来たが、その中に「Sさん」という一年後輩の学生さんがいた。
Sさんは小柄で、とても物静かな人だった。部屋にいても物音がしない。廊下を歩く時も遠慮がちに擦り足で歩き、帰る時は、律儀に何度も頭を下げて帰って行った。
北海道の兄弟が出て行った後の空き部屋を、そのSさんにお貸ししたが、一年後、Sさんも卒業して、郷里へ帰ることになった。
その引っ越しの日の光景を今でも覚えている。小豆色の大きな布団袋と本を、友だちが運転する小さな車の荷台に載せ、Sさんは、
「どうもお世話になりました」
と、首にかけていた手ぬぐいをとって、母と私に丁寧に頭を下げた。そして、小走りに走って、荷物を載せた荷台に飛び乗ると、まるで、絵本に出てくる馬車の御者みたいに、荷台に立ったまま、何度も後ろを振り返り、会釈しながら遠くなっていった。
昨年秋。ある日の午後、見知らぬ初老の人が玄関先に立っていた。
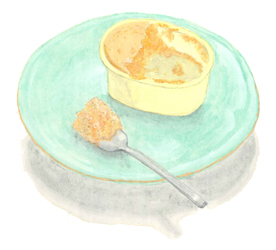  アルパジョンの「朝の八甲田」 |
「お忘れかと思いますが、私、昔こちらにお世話になっていたSと申します」
「……」
「こっちに来たものですから、ちょっとご挨拶に……」
「S……さん!?」
五十年ぶりだった……。Sさんはちょっと腰をかがめ、音をたてないように擦り足で居間に入って来ると、「お久しぶりです」と、床に手を突いて丁寧に挨拶し、お土産をくださった。髪が薄くなり、若い頃の面影はなかったけれど、ものごしは変わらぬままだった。
「先日、新聞で典ちゃんの記事を見たんですよ。いやぁー、もうびっくりして、懐かしくてね。東京に息子の家があるもんだから、今度行ったら、是非寄らせてもらおうと思って」
Sさんは、私が新聞に書いたエッセイを読んでくださったのだった。
下宿していた頃の話をすると、Sさんは「そうでした、そうでした」と、何度もうなずき、涙を流した。夕方、帰って行くSさんを門の外まで見送った。何度も振り返って、頭を下げる姿を見ながら、引っ越しの日に、馬車の御者みたいに荷台の上に立っていたSさんを思い出した。
いただいたお土産を、母といただいた。それが「朝の八甲田」だった……。柔らかいスフレで、スプーンですくうと、かすかに泡のような囁きが聞こえた。そっと舌に載せると淡雪のように消え、消えた直後にチーズのコクが立ちのぼる。その旨みは、去って行く懐かしい人の後ろ姿のように、いつまでも後を引いた。
© 2003-2012 Noriko Morishita, KAJIWARA INC.