2015年7月―NO.148
徹夜明けの「ペヤング」はうまかった。解放感と空腹には、ソース焼きそばのジャンキーな香りでなければならなかった。
麺のウェーブに絡んだ甘辛いソースのフルーティーな味が、青のりの風味が、疲れた体の欲求に応えてくれた。
まるか食品の「ぺヤングソース焼きそば」
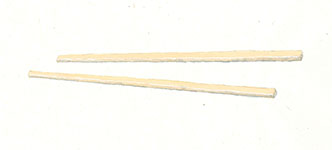 三十年前、私は週刊誌のコラムを書いていた。巷のおもしろい話を集めたコラムで、新聞社系の硬派な週刊誌としては異色の柔らかいページだったこともあり、世代を問わず人気のあるコラムだった。私は、取材の仕方も、文章の書き方も、そこで教わった。そのコラムを書いていた十年余りが、私の修業時代だった。
三十年前、私は週刊誌のコラムを書いていた。巷のおもしろい話を集めたコラムで、新聞社系の硬派な週刊誌としては異色の柔らかいページだったこともあり、世代を問わず人気のあるコラムだった。私は、取材の仕方も、文章の書き方も、そこで教わった。そのコラムを書いていた十年余りが、私の修業時代だった。
締め切りは毎週金曜日だった。当時はまだ原稿も手書きの時代で、私の他に二、三人のフリーライターが編集部の机に並んで原稿用紙のます目に向かい、書き上った原稿に編集者がチェックを入れ、OKになると見出しをつけた。
その見出しが、なかなか難しかった。決まった文字数で語呂もよく、読者の心をパッとつかむ言葉を探す。俳句を詠むみたいに、文字数を指折り数えながら言葉と格闘した。
そのコラムの担当編集者の中に、「ヤング」という言葉を多用するオジサンがいた。
「ヤングにバカ受けだ」
とか、
「そりゃもう古いよ。もっとナウな話題ないの?」
などと、今こうして書くだけで汗ばんでしまうようなフレーズを連発していた。七十年代の若者がさかんに使った流行語も、八十年代半ばにはとっくに古びて、オヤジだけが使う死語の代名詞になっていた。
その人はNさんと言った。三十代、四十代の編集者が多い中で、Nさんは五十歳くらい。いい人だった……。社員じゃない私のようなライターにも親切で、決して「上から目線」でものを言ったりしなかった。
私が初めての本を出すことになった時、Nさんは、
「僕、告知を書いてあげるよ」
と、快くコラムの最後のページに文章を書いてくれた。
「ナウなヤングにお勧めの本です」
と……。私はそれを読んで思わず、自分の顔が赤らむのを感じたが、ありがたい気持ちに変わりはなかった。
やがて私はコラムの仕事をやめ、編集部から遠ざかったが、ある日、新横浜の新幹線の改札口で、Nさんにバッタリ会った。
「大阪に転勤になったんですよ。単身赴任です。君も頑張ってね」
それがNさんと交わした最後の言葉になった。一緒にコラムを書いていたライターから、Nさんが病気で亡くなったと聞いたのは、それから数年後のことだった……。
 今月は、「ペヤングソース焼きそば」のことを書こうと思ったのに、つい前書きが長くなってしまった。というのも、「ペヤング」という、どこか軽薄な空気の漂う商品名である。このネーミングは一体何だろうと思ったら、
今月は、「ペヤングソース焼きそば」のことを書こうと思ったのに、つい前書きが長くなってしまった。というのも、「ペヤング」という、どこか軽薄な空気の漂う商品名である。このネーミングは一体何だろうと思ったら、
「ペアのヤングに、仲良く食べてほしい」
という意味だという。「ペアのヤング」がくっついて「ペヤング」。誕生は一九七五年だから、まさに「ナウなヤング」がイケイケだった時代の空気が、「ペヤング」というネーミングに籠っているのだ。
その「ペヤング」も、数えてみれば四十年。堂々たるロングセラーである。異物混入事件から半年ぶりの復活で、「売り切れ」が続出するほどの人気だという。そう聞いたら、なんだか久しぶりに食べたくなり、コンビニに買いに行った……。
私が頻繁に「ペヤング」を食べたのは、青春時代である。「青春」と言っても、中学・高校時代ではなかった。大学時代でもなかった。
花の三十代である。町ネタを取材して歩き、コラムを書いていたあの頃だ。同世代の友達はほとんど結婚して家庭を作り、子育てに奔走していた頃、私はようやく実家から独立し、一人暮らしを始めた。
原稿を徹夜で書き上げた明け方、ファックスの「カタカタカタ……」という送信音を聞きながら、安堵感と自由と、凶暴なほどの空腹感を感じた。そんな時、妙に食べたくなるのが「ペヤング」だった。 台所でお湯を沸かしながら、ペヤングの白い容器の蓋をとり、中から「かやく」と「ソース」の小袋を取り出す。カップ麺の容器はプラモデルみたいに軽く、乾いた音がした。ウェーブした乾麺に、かやくをパラパラと振り入れ、熱湯を注いで蓋をする。
台所でお湯を沸かしながら、ペヤングの白い容器の蓋をとり、中から「かやく」と「ソース」の小袋を取り出す。カップ麺の容器はプラモデルみたいに軽く、乾いた音がした。ウェーブした乾麺に、かやくをパラパラと振り入れ、熱湯を注いで蓋をする。
そして、待つこと三分……。徹夜明けの空腹に、ただ待つ三分は長い。私は硬めの麺が好みなので、いつも二分で切り上げた。四角い容器の角に、「湯切り」のための穴が三つあって、そこから湯を流すのだが、なにせ熱湯。流しのステンレスが急な熱で、ベコン!と大きく鳴った。
おおかた湯が出たところで、下手に容器を振って完全に湯を切ろうとすると、麺まで流しにどばーっと出て大惨事となった。ほどほどのところで蓋をあけ、ソースをまぜまぜして食す。
徹夜明けの「ペヤング」はうまかった。解放感と空腹には、ソース焼きそばのジャンキーな香りでなければならなかった。麺のウェーブに絡んだ甘辛いソースのフルーティーな味が、青のりの風味が、疲れた体の欲求に応えてくれた。
もう二十年以上、ペヤングを食べていないけれど、あれを食べたら、きっと思い出すだろう。「ナウなヤング」なんて言っていたオジサンのいた頃を……。そういうオジサンたちがイケイケだった頃の東京を……。
© 2003-2015 Noriko Morishita, KAJIWARA INC.