|
|
 身近な生活の中のおいしさあれこれを1ヶ月に1度お届けします 森下典子 |
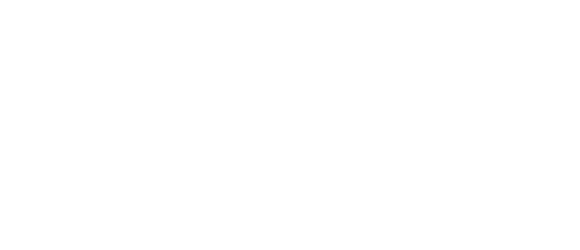 |
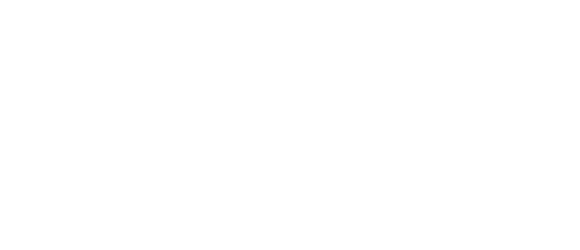 |
|
 |
 |
|||
| 2005年2月―NO.29 | |||||
| |||||
| |||||
あの頃、日本の一般家庭の台所には、オーブンがなかった。芋の煮っころがしや鯖の味噌煮を作るのにオーブンなど必要なかったのだが、「うちでケーキを焼く」という言葉の響きには、きらめくような憧れがあった。 その憧れは、案外早く現実のものになった。私が高校生になった頃、わが家の台所にオーブンが入った。私はガスレンジの下に組み込まれたオーブンの扉を空けたり、閉めたりした。 たちまち母が、洋菓子やパン作りに熱中した。学校から帰ると、玄関まで、ほんわりと温かくうす甘い匂いが漂っている。 「おかえりー!今、お菓子を焼いてるのよ」 と、台所から母の声がする。 「うおーっ!」 食べ盛りの私と弟は、雄叫びを上げた。 母がミトンの手袋でオーブンの扉を開け、黒い鉄板を引き出す。ある時はマドレーヌ、ある時はクッキー、そしてまたある時は動物の恰好をしたパンがこんがりと焼けていた。 母はケーキやパイにも挑戦し、いろいろな洋菓子を作ってくれたが、最初のうちは失敗作も多かった。 何度も失敗したのはシュークリームだった。シュー皮のタネを搾り、オーブンで焼くと、ぷーっとキャベツのように膨らんで、中に空洞ができるはずなのだが、この皮がなかなか膨らまない。せっかく膨らんでも、オーブンを開けたら、しぼんでしまったこともあった。 「あー、また失敗だわ」 母が悔しそうにつぶやきながら、できそこないのシュー皮を皿に積み上げると、私は、内心、ほくほくした。 | |||||
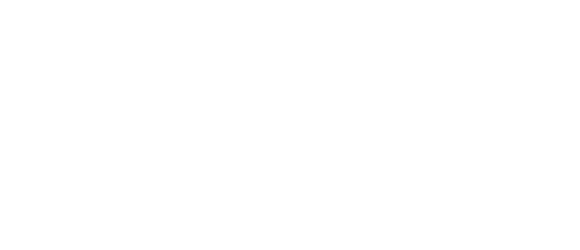 |
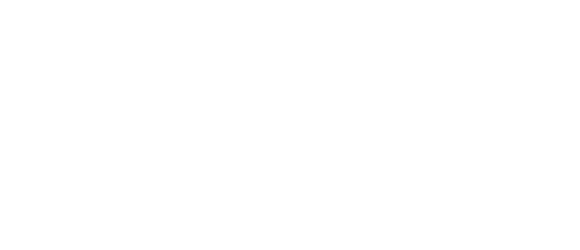 |
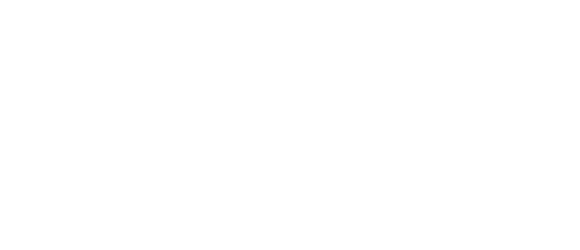 |